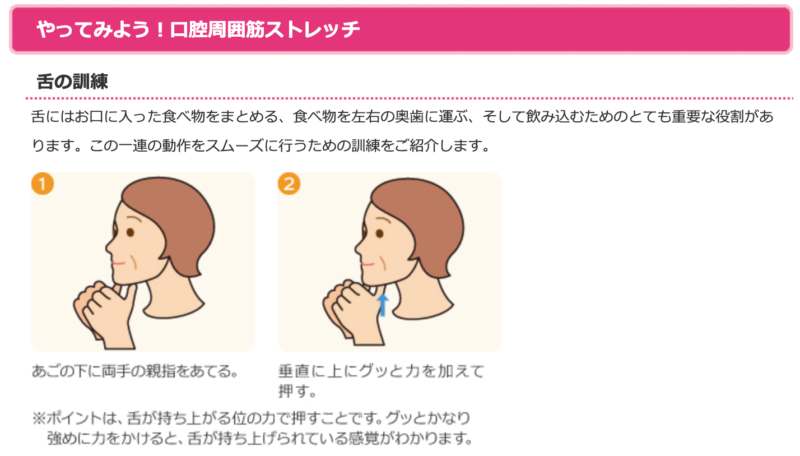滑舌(かつぜつ)について語り始めるとおそらく私は、
日が暮れて夜が明けてモーニングを食べ終わってまたもや再開して・・何時間喋るでしょうか。。
それくらい、悩んできました。
だって、「ブツブツさん」だったから。
ブツブツいうだけで何を言ってるかわからない人だったのです。
どれくらいのブツブツさんだったかというと、
中学の部活の最中、顧問の先生に、
「集合かけて」と言われて、
「しゅ、しゅご・・・」どうしても言葉をだすことが
できなかったと言うくらいのブツブツさんでした。
なぜブツブツと言われるのか、
他の人と何が違うのか、
声の大きさなのか
音の高低なのか
話すテンポなのか
文章のセンテンスなのか言葉選びなのか
文頭に何を持ってくればいいのか
または・・・
このようなことについては散々考えたのです。
そして、
最終的に
「滑舌」という壁に当たります。
1.早口言葉では直らない
滑舌という話題が出た時に、ほとんどの人が
「早口言葉をすればいい」と答えます。
本当にそうでしょうか。
そもそも、滑舌がよくない人と言うのは、
早口言葉を早口で言えない人のことではないでしょうか。
そこへ早口言葉の練習をいくらしたところで、
できるようにはならないのではないでしょうか。
私はできませんでした。
1年間毎日30分間、外郎売をやりました。
(ういろううり・有名な早口言葉の長文です)
「努力は裏切らない!」とよく言いますが、
この時は完全に裏切られました。
今になって思うことはこうです。
ピアノに例えると、
「鍵盤を抑えることも知らず、(音をならせていないのに)
ショパンのノクターンの練習をしていた」
マラソンに例えると、
「匍匐前進でマラソンしようとしていた」
大阪から東京に向かって南に走り始めた
すごく遠かったです。
パスポート必要でした。
通れない国なんかもあって、、
(すみません本題に戻ります)
2.呼吸の量が足りていない
人前で話をするための声の出し方など、
系統立てて学んだことのない方がほとんどです。
ですが、圧倒的に呼吸の量が足りていない人が多いと言うのが、
ここ1年ほど演技指導という形で色んな方々に関わってきて感じるところです。
呼吸の量というのは口の中に響かせる空気の量のことです。
子供の頃使ったリコーダーを連想していただきたいのですが、
吐き出す呼吸が少ないと、音がきれいに響きません。
口の中に響かせる時、息を上顎(うわあご)に当てる意識を持つと、
わかりやすいでしょう。
「カッ!」
と叫んでみてください。
上顎に空気があたった感じがしませんか?
3.正しいフォーム
スポーツにはなんでも正しいフォームがありますね。
バッターボックスに入っても、外側にバットを構えていては、
永遠にヒットは打てません(暴投とかのツッコミはなしで)
伝統ある滑舌の練習方法でも、
やり方を考えるべきものがあります。
アイウエオ
イウエオア
ウエオアイ
エオアイウ
オアイウエ
ご存知の方も多いでしょう。
最初の問題はサ行です。
サシスセソ
シスセソサ
スセソサシ
セソサシス
ソサシスセ
この時点で子音(しいん)が2種類出てきています。
サ行とシャ行です。
つまり、
サスィセソ
のサ行と、
シャシシュシェショの
シャ行の2種類が入っています。
そんなわけで、
サ行をきれいに発音するには!
(口を動かしてみてください)
サスィスセソ
スィスセソサ
スセソサスィ
セソサスィス
ソサスィスセ
シャシシュシェショ
シシュシェショシャ
シュシェショシャシ
シェショシャシシュ
ショシャシシュシェ
サ行とシャ行では、
舌の位置が違いますね。
sa si su se so
sha shi shu she sho
と、ローマ字にするとよくわかります。
こんなのをワークショップでやっていると、
なんと、
「思っていたのと舌の位置が違う!!」
なんて人が現れてびっくりしました。
確かに彼女は普段から、
サ行とタ行の区別がつきにくい発音をされていたのです。
「サ」の音は、
舌先を前歯下側の根元に当てて発音しますが、
これが上の歯に当たっていたそうです。
舌先が上だと「タ」としか発音できません。
このタイプは何故か関西に多いようです。
ある有名アナウンサーの先生は、
「関西人は日本一サ行がタ行に近い」
とおっしゃっていました。
日本一って・・笑。
滑舌の話はまだまだありますが
とりあえずこの変で、いや辺で。
今日も素敵な1日を。
ちゃお