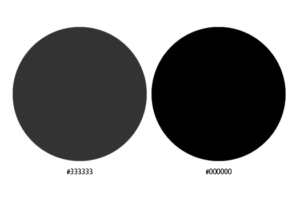栗原ちゃおです。
ライフワークで劇団やっています。
役者名が栗原ちゃおです。
最近よく聞かれること。
「セリフってどうやって覚えるの?」
あー、覚える、そうですね、覚える、、確かに、覚えないことには芝居はできません。
覚えないことには何も始められないので、オーディションのお題がコレですよって
事前に台本渡されたりするんです。当然すぐに覚えて、どう演じるかと言うことに注力するんですよね。
だから私個人としてはどうやって覚えるなんて言うことをあんまり考えたことがなかったんです。
覚えるのはスタートであって、覚えただけでは演技とはいえません。
それでもあまりにも聞かれるので、
「どうやって覚えるか」ということに的を絞って考えてみることにしました。
ほとんどの人が覚え方を間違っています。
台本を「ジーーーーーーー」と、見ています。
多分記憶領域が違うんだと思います。
「ジーーーー」と見たり読んだりしていれば、
学校の勉強のように、質問された時に「書いたり」「暗唱したり」できるかもしれません。
しかしセリフとして言葉を発する時、紙に書く必要はありません。
聞いてる人は台本を持っていません。
間違えてよいわけではありませんが、
「てにをは」を完璧にするよりも、
文章やストーリーの主旨を感じ取ることが重要です。
暗記と圧倒的に違うのは、
「書く」のではなく「表現する」ということです。
「文字に起こす」のではなく「音声で伝える」と言うことです。
「書く」ものは書いて覚えればいいですね。
「手が勝手に動く感覚」を感じたことのある方も多いと思います。
「書いて覚えたもの」は口で言えなくてもペンを持てばかけたりするんですよね。
自転車も車の運転も、
反射的に身体が動いて走ったり止まったりしています。
「えっと、、止まる時は、、そうそうブレーキだ。」なんて考えていたら大変なことになります。
この
「反射的に体が勝手に覚える感覚」を使うと
台本はかんたんに頭に入ります。
赤ちゃんは
「反射」で言葉を覚えるように。
その前にやっておくことがあります。
「キーワードをマークする」ことです。
例えばこんな文章があった場合、
でも、仕方がないわ、生きていかなければ!
ね、ワーニャ伯父さん、生きていきましょうよ。
長い、はてしないその日その日を、いつ明けるとも知れない夜また夜を、じっと生き通していきましょうね。運命がわたしたちにくだす試みを、辛抱づよく、じっとこらえて行きましょうね。
今のうちも、やがて年をとってからも、片時も休まずに、人のために働きましょうね。
そして、やがてその時が来たら、素直に死んで行きましょうね。
あの世へ行ったら、どんなに私たちが苦しかったか、どんなに涙を流したか、どんなにつらい一生を送って来たか、それを残らず申上げましょうね。すると神さまは、まあ気の毒に、と思ってくださる。
(ワーニャ伯父さん チェーホフ 出典:青空文庫)
エンディング直前の長台詞の4分の1です。
キーワードをマークします
でも、仕方がないわ、生きていかなければ! (間)
ね、ワーニャ伯父さん、生きていきましょうよ。
長い、はてしないその日その日を、いつ明けるとも知れない夜また夜を、じっと生き通していきましょうね。運命がわたしたちにくだす試みを、辛抱づよく、じっとこらえて行きましょうね。
今のうちも、やがて年をとってからも、片時も休まずに、人のために働きましょうね。
そして、やがてその時が来たら、素直に死んで行きましょうね。
あの世へ行ったら、どんなに私たちが苦しかったか、どんなに涙を流したか、どんなにつらい一生を送って来たか、それを残らず申上げましょうね。すると神さまは、まあ気の毒に、と思ってくださる。
キーワード→「カギ」となる「コトバ」を見つける作業です。
キーワードを並べるとこんな感じです。
生きていかなければ
ワーニャ伯父さん、生きていきましょう
はてしないその日その日 いつ明けるとも知れない夜また夜 じっと生き通し
運命がわたしたちにくだす試み こらえて
今も、年をとっても、休まず 人のために働き
やがて 素直に死んで
あの世へ 私たちが苦しかった 涙を流した つらい一生
残らず申上げ
神さま 気の毒
頭に入れるコツは、
「台本から目を離すこと」
文字を追っている限り、なかなか口は動いてくれません。
文字を読んでいる限り覚えられません。
文字から目を離し、前を向いて声を出してみましょう!!
公共の場所にいる方は、ひそひそ声でも構いません。
さぁ、1行目をどうぞ!!
あ、出てきませんか?
すぐに目を落として台本を一瞬盗み見たら、
またすぐに前を見て喋ってみます。
意外と2行目くらいまで一気に言えた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「でも」しか言えなかった〜!なんて方も、大丈夫です!最初なんだから!!
最初に覚えられる長さの差はありますが、繰り返すとだんだんそれが長くなってきます。
長い文章も頭に入りやすくなります。
セリフは頭で覚えるのではなく、
「口に覚えさせるもの」なのです。
キーワードをチェックする。
前を見て話す。
これを繰り返すうちに、
「ここだけいつも忘れる」または間違えるところが出てきます。
文の最初がでてこないことが多いですね。
例えば、
今のうちも、やがて年をとってからも、
これがでてこない時は、
前文の文末とつなげて「口に覚えさせ」ます。
こらえて行きましょうね。
今のうちも、やがて年をとってからも、
こんな地味な作業の繰り返しくりかえしです。
繰り返し繰り返して、
「口がセリフを覚えた時」
そこがスタート地点です。
ようやく材料が揃いました。
今日も素敵な1日を♪
ちゃお♪